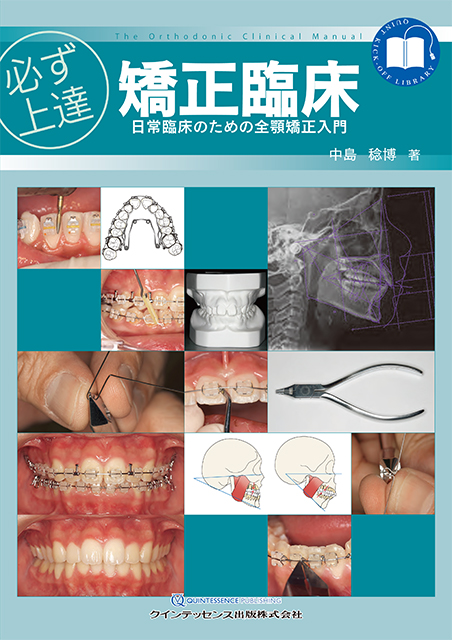社会|2025年4月14日掲載
「上顎側切歯から広がる歯科の世界 ~ジェネラリストのこだわり~」の限局的なテーマで注目を集める
第47回北九州歯学研究会発表会開催
さる4月13日(日)、パピヨン24ガスホール(福岡県)にて、第47回北九州歯学研究会発表会(白石和仁会長)が総勢160名を集めて開催された。
白石会長による開会の辞ののちに新人発表が行われ、竹中 崇氏が「残根を活かす ~矯正的挺出法を用いたその活用法~」、河島紘太郎氏(広島県開業)が「補綴前処置の重要性を考える」の演題にてそれぞれ新人らしからぬ充実の内容を発表した。
続いて、今回の目玉となるシンポジウム「上顎側切歯から広がる歯科の世界 ~ジェネラリストのこだわり~」が行われた。本シンポジウムは今大会の実行委員長である樋口 惣氏を中心に、上顎側切歯にフォーカスを当て、歯内療法、歯周治療、修復治療、補綴治療などの基本治療に対する北九州歯学研究会会員のこだわりを、臨床例をとおして紹介する企画として考案された。司会・進行を松延允資氏と松木良介氏が務め、トップバッターとして中島稔博氏が右側上顎側切歯を根管治療と歯周外科治療で、左側の欠損部顎堤にCTGで対応したケースを供覧し、単純なように見えても、実は状況に応じてさまざまな対応が必要となる上顎側切歯部の特徴について紹介し、シンポジウムへの導入の役割を果たした。
第一部となる「エンド・修復」パートでは、瀬戸泰介氏、倉富覚、氏、青木隆宜氏、竹中氏、津覇雄三氏、樋口克彦氏が登壇し、上顎側切歯の根管解剖や根尖部の弯曲根管、レッジ(出っ張り)のある症例の攻略法や外科的歯内療法の病理学、そして上顎側切歯のう蝕やそのCR修復について論じた。
昼食を挟み、第二部となる「ペリオ・補綴」パートでは、河島氏、力丸哲哉氏、田中憲一氏、青木氏が登壇し、斜切痕(口蓋溝)に起因する骨内欠損への対応、また上顎側切歯部に対するダイレクトベニアやポーセレンラミネートベニアを用いた補綴治療などが紹介された。
第三部となる「欠損」パートでは、力丸氏、芳賀 剛氏、筒井祐介氏が登壇し、上顎側切歯部に対するプラスティックサージェリーやGBR後にインプラント埋入を行った症例などが供覧された。
最後のまとめ症例として小松智成氏(山口県開業)は、術後20年が経過する上顎側切歯を含む全顎的な長期経過症例を供覧し、一歯に対する治療のこだわりが最終的には患者のためにもなることが示されシンポジウムが締め括られた。
次回の第48回北九州歯学研究会発表会は、2026年2月15日(日)にJR九州ホール(福岡県)にて開催される予定である。
(※なお、実名を挙げた歯科医師の先生方は特に記載がなければすべて福岡県開業)